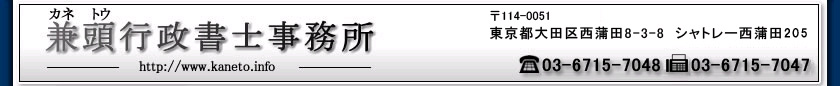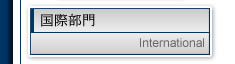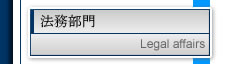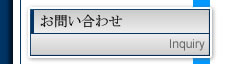|
 |
 契 約 契 約 |
契約とは、一定の法律効果の発生を目的とする当事者間の約束(合意)をいいます。
誰とどのような内容の契約をするかは、当事者が自由に決める事が出来ます。
これを契約自由の原則といいます。
しかし、だからと言ってどんな内容の約束をしても法律上有効かと言うとそうはいきません。
例えば、今流行の「援助交際」の契約などは無効です。(民法90条)
契約が有効に成立するということは、当事者間に債権責務の関係が生じることです。
債務者が、債務の履行しないと裁判所に訴えて債務者の財産に強制執行をすることができます。
このように契約が有効であるということは、債権者に強大な力を与えることを意味します。
したがって、法は以下の要件を満たした場合に限り契約を有効とします。 |
 1.契約内容を確定することができること 1.契約内容を確定することができること |
何を決めたのかがはっきりと分かるものでなければなりません。
はっきりしない場合は、法律の規定、慣習、条理、当事者の意思などを基準としてその内容を解釈に
よって確定します。解釈によっても確定できないときは無効となります。 |
 2.契約内容を実現することができること 2.契約内容を実現することができること |
常識的に見て契約内容どおりの履行ができないと一般に考えられる場合は、その契約は無効となります。
例えば、「火星に行ってそこにある岩石をもってくれば1億円あげます」といった契約をしても無効です。
現在の科学技術から見て人間が火星に行くことは不可能だからです。 |
 3.契約内容が適法であること 3.契約内容が適法であること |
強行法規に違反する契約をしても無効となります。(民法91条)
例えば、不動産の賃貸借契約で賃借人に不利な契約をしても無効となります。
(借地借家法9条、30条)
労働基準法に違反する労働契約をしても無効となります。(労働基準法13条)
法律で認めない物権を契約で定めても無効です。(民法175条)
利息制限法に違反する利息を契約で定めても無効です。(利息制限法1条)
|
 4.契約内容が社会的に妥当であること 4.契約内容が社会的に妥当であること |
公序良俗に違反する契約をしても無効となります。(民法90条)
例えば、「人殺しをすれば1千万円やる」という契約をしても無効となります。
賭博に使うことを知ってする金法が、このようなことを認める訳にはいかないからです。 |

 1.権利能力があること 1.権利能力があること |
権利義務の主体となることのできる法律的な資格をいいます。
自然人に付いては、生まれたときに権利能力を取得し、(民法1条の3)死亡によって消滅します。
ただし、これには3つの例外があります。不法行為に基づく損害賠償請求(民法721条)、
相続(民法886条)、遺贈(民法965条)については、「胎児」に権利能力を認めています。
法人(株式会社や有限会社など)は、法律上の要件を満たしたときに権利能力を取得します。 |
 2.意思能力があること 2.意思能力があること |
自分の行為の結果を予測し、その利害得失を正確に判断できる知的能力を言います。
各個人は、その意思に基づかなければ権利を得たり、義務を負わされたりすることはないというのが
近代私法の大原則です。これを「私的自治の原則」といいます。従って正常な判断能力のない
場合には、その行為は無効となります。
例えば、庸司、高度の精神病者、泥酔者などは意思能力がないとされていますので、その者の
行為は無効です。 |
 3.行為能力があること 3.行為能力があること |
法律行為を単独で有効にすることが出来る法律上の能力を言います。
法律は、以下の様に判断能力が十分でない者を類型化し、これに保護者をつけて保護しています。
(1)未成年者(民法4条)
原則として法定代理人(親権者)の同意が必要です。同意のない行為は、取り消すことが出来ます。
(2)成年被後見人(民法9条)
成年後見人が代理して行為をすることになります。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する
行為は単独で出来ます。
これ以外の行為をしても、すべて取り消すことが出来ます。
(3)被保佐人(民法16条)
民法規定の行為をするには、保佐人の同意を得る必要があります。
同意なしにした行為は、取り消すことが出来ます。
(4)被補助人(民法16条)
民法規定の行為をするには、補助人の同意を得る必要があります。
同意なしにした行為は、取り消すことが出来ます。 |
 4.意思と表示に不一致がないこと 4.意思と表示に不一致がないこと |
(1)心裡留保(民法93条)
嘘を言うことをいいます。
例えば、あげる気もないのに「この自動車をやるよ」といった場合などがこれに当たります。
この場合、嘘を吐いた者を保護する必要がないので法はこれを有効とします。
しかし、相手が嘘に気付いているとき、または、過失でこれに気が付かなかったときは無効となります。
(2)通謀虚偽表示(民法94条)
相手と申し合わせて嘘を言うことを言います。
この場合は、無効となります。
ただし、両者が通じていることを知らない第3者に対しては、無効を主張することが出来ません。
例えば、AとBga相談し、A所有のマンションをBに売却したことにして、登記名義をBにした場合、
Bが勝手にそのマンションを事情を知らないCに売り、C名義に所有権移転登記をしてしまうと
AはCに対し、自分の所有権を主張することが出来なくなります。
くれぐれもこのような「仮想売買」はしないよう気をつけたほうがいいかと思います。
(3)錯誤(民法95条)
自分で勝手に思い違いをすることをいいます。
この場合は、契約内容の重要な部分に食い違いがあると無効となります。
ただし、錯誤者に重大な過失があるときは、無効を主張することが出来ません。
例えば、有名ブランドのカバンだと思って買ったところ実は偽者であった場合など。
その契約は無効となります。 |
 5.意思決定過程に瑕疵がないこと 5.意思決定過程に瑕疵がないこと |
(1)詐欺(民法96条)
だまされて思い違いをして契約した場合を言います。
この場合は、契約を取り消すことが出来ます。
ただし、事情を知らない第3者に対しては、だまされて契約したことを主張できません。
(2)強迫(民法96条)
脅されて怖くなり契約した場合を言います。
この場合は、契約を取り消すことが出来ます。
消費者契約法4条は、上記の「詐欺」「強迫」に至らない場合であっても「誤認」「困惑」によって
契約したときは、一定の要件を備えればその契約を取り消すことが出来るとしています。 |

 |
(1)契約書を作成すること
口頭だけでも契約は有効に成立します。これを諾成契約といいます。
しかし、後日のトラブルを避けるため、契約書を作成することをお勧めします。
裁判になった場合、重要な証拠となります。
(2)実印を押し、印鑑証明書を付けること
認印でも構いませんが、個人の場合は市区町村役場に登録した印鑑を、会社の場合は
登記所に登録した代表者印を押すことをお勧めします。
尚、会社の場合は代表者の資格証明書(会社の登記簿謄本)を付けるがよいでしょう。
裁判でその契約書が本物かどうかが問題となった場合、本物であることを証明しなければなりません。
民事訴訟法228条4項は、「私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に
成立したものと推定する」と規定しています。従って契約当事者の所名又は押印があれば、これを
争う側で偽造であることを証明しない限り本物として扱うことになっています。
実印が押されているとこの証明が容易になります。
(3)契約書には印紙税法の定める印紙を貼ること
この印紙を貼らなくても契約は有効に成立します。しかし、印紙を貼らないと脱税になり、
過怠税を徴収されることがありますのでご注意が必要です。(印紙税法20条)
(4)契約書が2枚以上になる場合は、各用紙との間に割印を押すこと
これは、後から差し替えられることを防止するために必要です。
(5)代理人によって契約する場合は、委任状を交付すること
委任状には、代理権の濫用を防止するため、代理人の代理権の範囲を具体的に記載する必要が
あります。白紙委任は絶対にしないように。
後でおんでもない責任を取らされることがあります。(民法110条)
(6)契約書には「捨印」をしないこと
捨印は、契約書の作成後に文字の訂正をするのには便利ですが、勝手に訂正するなどして
トラブルの原因になりますので避けるべきでしょう。 |

|
|
COPYRIGHT(C) 兼頭行政書士事務所 ALL RIGHTS RESERVED.
|
|